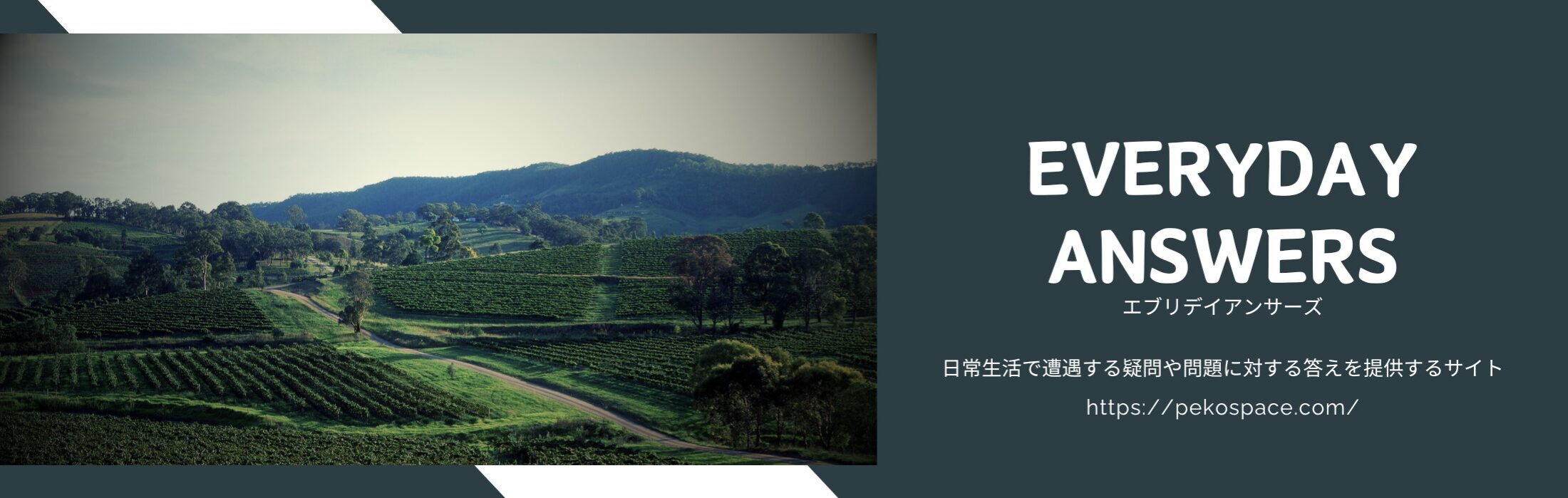日本でエキゾチックペットとして注目を集めている「オポッサム」。
独特の姿と愛らしい表情で人気を博していますが、日本で飼育するとなると知っておくべきことがたくさんあります。
「死んだふり」で有名なこの動物は、実は70種類以上もの仲間がいるのをご存知でしょうか?
しかし、日本の住環境や入手可能性を考えると、すべての種類が飼育に適しているわけではありません。
本記事では、日本でオポッサムを飼うなら小型種が現実的な選択肢である理由と、その具体的な飼育方法について詳しく解説します。
目次
日本で飼育できるオポッサムの種類と特徴を知ろう

- 日本におけるオポッサムの入手可能性
- オポッサムの生態と特徴を理解する
- 大型種と小型種の飼育環境の違い
- オポッサムの飼育に必要な専門知識
日本におけるオポッサムの入手可能性

(Cody Pope, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)
オポッサムは南北アメリカ大陸に生息する唯一の有袋類として知られています。70種以上ものオポッサムが記録されていますが、日本で入手できる種類は限られています。
最も流通しているのは「ピグミーオポッサム」と呼ばれる小型種です。この種は手のひらサイズの小さな体が特徴で、全長約20cm(体の部分は約10cm)、体重約100gとハムスターより少し大きい程度の大きさです。
一方、「キタオポッサム」などの大型種は、体長約75cm、体重4~6kgにもなり、中型犬や大きめの猫と同等のサイズです。オポッサム属の全種は「特定外来生物」には指定されていないため日本での飼育は合法ですが、キタオポッサムは流通量が非常に少なく、一般的なペットショップでの取り扱いは稀です。そのため、個人での入手は極めて困難です。
価格帯としては、比較的入手しやすいピグミーオポッサムでも2万円~5万円程度と、このサイズの小動物としては高額です。流通量が少ないため、価格の変動も大きいです。
オポッサムの入手ポイント
- 日本で入手しやすいのは主にピグミーオポッサムなどの小型種
- オポッサム属は「特定外来生物」ではないため飼育自体は合法
- 信頼できるペットショップで購入し、適切に輸入された個体か確認する
- ピグミーオポッサムの価格は2〜5万円程度と小動物としては高額
オポッサムの生態と特徴を理解する

オポッサムは有袋類の一種で、カンガルーやコアラと同じように子育て用の袋「育児嚢(いくじのう)」を持っています。しかし、ピグミーオポッサムは例外的に育児嚢を持たず、生まれた子どもは母親の背中や尻尾にしがみついて育ちます。この特徴から「コモリネズミ」とも呼ばれています。
オポッサムの最も有名な特徴は「死んだふり」です。天敵に襲われると本能的に横たわり、舌を出して死んだように見せかけます。これは「擬死反射」と呼ばれる防衛行動で、オポッサムは特に上手にこの行動を取ることができます。
また、樹上生活に適応しており、鋭いツメを持ち、長い尻尾は第5の手足のように器用に使います。夜行性の動物で、日中は巣で休み、夜間に活動します。寿命は野生下で約4年、飼育下では8年程度とされています。
大型種と小型種の飼育環境の違い
大型種と小型種では必要な飼育環境が大きく異なります。大型種は猫と同等以上の大きさがあるため、広いスペースが必要になり、日本の住宅事情では飼育が困難です。また、大型種は臭いが強く、近隣トラブルの原因になる可能性もあります。
対照的に、ピグミーオポッサムはリスやハムスター用のケージで飼育可能です。ただし、樹上生活をするため、高さのあるケージが望ましいでしょう。また、特定の温度環境(約25℃)を維持する必要があり、ヒーターなどの温度管理機器も必要になります。
縄張り意識が強く単独行動を好むため、複数飼育は避けた方が良いでしょう。また、脱走防止のため、金網タイプのケージを使う場合は隙間に注意が必要です。
以下の表で、大型種のキタオポッサム(バージニアオポッサム)と小型種のピグミーオポッサム(ハイイロジネズミオポッサム)の主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | キタオポッサム | ピグミーオポッサム |
|---|---|---|
| 品種名 | バージニアオポッサム | ハイイロジネズミオポッサム |
| 学名 | Didelphis virginiana | Monodelphis domestica |
| 分類 | フクロネズミ科(Didelphidae) | フクロネズミ科(Didelphidae) |
| 体長 | 35~55cm(尾を含めると約75~100cm) | 10cm(尾を含めて20cm程度) |
| 体重 | 4~6kg(地域によって異なる) | 80~150g(個体差あり) |
| 生息地 | 北アメリカ(米国、カナダ、メキシコ) | 南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど) |
| 寿命 | 野生で2~3年、飼育下で4~7年 | 5~8年 |
| 食性 | 雑食性(果物、昆虫、小動物、腐肉など) | 雑食性(果物、昆虫、小型動物) |
| 育児嚢(フクロ) | あり | なし |
| 行動特性 | 夜行性、単独行動、擬死(死んだふり)をする | 夜行性、単独行動、主に樹上で活動するが地表も移動 |
| 臭いの強さ | 通常は強い体臭はないが、擬死時に悪臭を放つ | 体臭は少ない |
| 飼育の難易度 | 非常に困難(輸入・流通なし、獣医不足) | やや難しい(流通が限られる、夜行性、温度管理が必要) |
この表からも分かるように、体のサイズだけでなく、育児嚢の有無や臭いの強さ、飼育の難易度など、多くの点で両種には違いがあります。
特に日本での飼育を考える場合、ピグミーオポッサムの方が現実的な選択肢だと言えるでしょう。
オポッサムの飼育に必要な専門知識
オポッサムはまだペットとしての歴史が浅いため、飼育に関する情報が少なく、専門的な知識を持つ獣医師も限られています。病気や怪我の際の対応が困難なケースも多いため、基本的な健康管理について理解しておくことが重要です。
ピグミーオポッサムがかかりやすい病気には、皮膚糸状菌症(かゆみやフケ、脱毛などの皮膚トラブル)やコクシジウム症(原虫感染による下痢や腸炎)などがあります。また、ストレスによる自咬症(自分の体を噛む行動)も見られることがあります。
飼育者は、オポッサムの行動パターンや健康状態の変化に敏感になり、早期発見・早期治療ができるよう心がけましょう。また、エキゾチックアニマルに対応できる動物病院をあらかじめ確認しておくことも大切です。
日本でピグミーオポッサムを飼育する方法とポイント

- 適切な飼育環境の作り方
- 健康的な食事と日々のケア
- 健康管理と病気の予防
- ピグミーオポッサムを飼う際の心構えと責任
適切な飼育環境の作り方

(The original uploader was Dawson at English Wikipedia., CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)
ピグミーオポッサムの飼育には、高さのあるリス用や爬虫類用のケージが適しています。
金網タイプのケージを使用する場合は、隙間から脱走しないよう注意が必要です。ケージ内には巣箱を設置し、その中に新聞紙やガーゼを敷いて、落ち着ける場所を作りましょう。ただし、綿は誤食の危険があるため使用しないでください。
最適な室温は約25℃です。気温が下がると冬眠状態になることがあるため、爬虫類用のヒーターなどで温度を一定に保つことが重要です。飼育下での冬眠はリスクが高いため、避けるように管理しましょう。
餌入れと水入れは小動物用のものでかまいませんが、給水器は使いにくいようなので、深めの容器に水を入れて与える方が良いでしょう。ただし、こぼれにくいよう工夫が必要です。
ケージは脱走防止のため、扉の開閉時には特に注意してください。清掃は定期的に行いますが、毎日行うとストレスになるため、適度な頻度を心がけましょう。
飼育環境を作るポイント
- 高さのあるリス用・爬虫類用ケージが適切(脱走防止に注意)
- 巣箱には新聞紙やガーゼを敷く(綿は誤食の危険があり不可)
- 室温は約25℃を維持し、冬眠を防止する
- 給水器より深めの容器での給水が適切
- 清掃は適度な頻度で行い、過度な清掃はストレスの原因に
健康的な食事と日々のケア
ピグミーオポッサムは雑食性で、野生では果実、昆虫、種子などを食べています。
飼育下では、ハムスターやリス用のエサを細かくして、細かく切った果物を混ぜたものを与えると良いでしょう。朝と夕方の1日2回、餌を与えるのが理想的です。
タンパク質補給のために、ゆで卵、ミルワームなどの昆虫類、茹でた鳥のささみ、栄養補給ゼリーなどを補助食として与えると栄養バランスが保てます。また、夜行性のため、夕方に餌を与えると活動に合わせることができます。
水は毎日新鮮なものに取り替え、清潔さを保ちましょう。食器類も定期的に洗浄し、衛生状態を維持することが重要です。
また、ピグミーオポッサムは臭いが独特で、特に夏場は強く感じることがあります。定期的な清掃と換気を心がけましょう。
健康的な食事と日々のケア
- 基本食:ハムスター・リス用エサを細かくし、果物を混ぜたもの
- 補助食:ゆで卵、ミルワーム、ささみ、栄養補給ゼリーでタンパク質補給
- 給餌は朝夕2回、特に夕方は夜行性の活動パターンに合わせる
- 水と食器は毎日清潔に保つ
- 独特の臭いがあるため定期的な清掃と換気が必要
健康管理と病気の予防
ピグミーオポッサムの健康を維持するためには、清潔な環境と適切な温度管理が欠かせません。
不衛生な環境や過度なスキンシップはストレスとなり、免疫力や体力の低下を引き起こします。
定期的に体重を測定し、食欲不振や行動の変化などの異常が見られたら、早めにエキゾチックアニマル対応の動物病院に相談しましょう。特に、皮膚のかゆみや脱毛、下痢や血便、体重減少などの症状は要注意です。
コクシジウム症は健康なピグミーオポッサムでも発症しにくいですが、ストレスや栄養不足で免疫力が低下すると発症しやすくなります。適切な栄養管理とストレスの少ない環境づくりが予防につながります。
また、自咬症(自分の体を噛む行動)はストレスが原因で起こることが多いので、生活環境の見直しが必要です。傷口には獣医師の指示に従って適切な消毒を行いましょう。
健康管理と病気予防
- 清潔な環境と適切な温度管理が健康維持の基本
- 定期的な体重測定と行動観察で異常を早期発見
- 皮膚トラブル、消化器症状、体重減少は要注意サイン
- コクシジウム症は免疫力低下時に発症しやすい
- 自咬症はストレスが原因なので環境改善が必要
ピグミーオポッサムを飼う際の心構えと責任
エキゾチックアニマルであるピグミーオポッサムを飼うには、その生態をよく理解し、終生飼育の責任を持つことが重要です。
一時的な興味や流行で飼い始め、飽きてしまうことがないよう、十分に検討してから迎え入れましょう。
ピグミーオポッサムはまだペットとしての歴史が浅く、情報が限られています。また、病気になっても診療してくれる動物病院が少ないという現実もあります。そのため、飼育前にエキゾチックアニマル対応の動物病院の有無を確認しておくことも大切です。
また、ピグミーオポッサムは夜行性のため、昼間は静かな環境を提供し、夜間の音や明かりには配慮が必要です。家族全員の理解と協力も欠かせません。
何より、生き物の命を預かるという責任を自覚し、その生涯に寄り添う覚悟を持ちましょう。飼育が難しくなった場合のことも考え、相談できる専門家やコミュニティとのつながりを持っておくことも重要です。
飼育者としての心構えと責任
- 終生飼育の責任を持ち、一時的な流行で飼わない
- 飼育前にエキゾチックアニマル対応の動物病院を確認する
- 夜行性に配慮し、昼間は静かな環境を提供する
- 家族全員の理解と協力を得る
- 困ったときに相談できる専門家やコミュニティとつながりを持つ
「日本でオポッサムと暮らすための準備と正しい飼い方」についての総括
記事のポイントをまとめます。
- 日本で飼育可能なオポッサムは主にピグミーオポッサムなどの小型種である
- オポッサムは「特定外来生物」ではないため飼育自体は合法だが、輸入には「種類名証明書」が必要
- ピグミーオポッサムは体長約10cm、体重約100gと小型で、価格は2〜5万円程度
- 大型種は体長75cm、体重4〜6kgと大きく、日本の住環境では飼育が困難
- ピグミーオポッサムは縄張り意識が強いため、1匹で飼育するのが望ましい
- 飼育には高さのあるリス用ケージ、巣箱、25℃を維持するヒーターが必要
- 餌はハムスター用フードと果物の混合食に加え、タンパク質源を補助食として与える
- 夜行性のため昼間は静かな環境を提供し、夜間の活動に配慮する
- かかりやすい病気には皮膚糸状菌症やコクシジウム症があり、早期発見が重要
- ピグミーオポッサムはペットとしての歴史が浅く、対応できる動物病院が限られている
本記事では、日本でオポッサムを飼育する場合、ピグミーオポッサムなどの小型種が現実的な選択肢である理由と、その適切な飼育方法について解説しました。
オポッサムは魅力的なエキゾチックペットですが、その特性や必要な環境をしっかりと理解し、責任を持って飼育することが大切です。
ペットとの出会いは長い付き合いの始まりです。十分な情報収集と準備の上で、素敵な共生関係を築いていきましょう。